※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

「育休中のパパは何をしたらいいの?」
パパも育休を取って当たり前という時代になりました。
しかし、実際に育休中に何をしたらいいかわからないパパは多いですよね。
本記事では、パパが育休中にやること10選と、気が利くパパになる方法をお伝えします。
本記事をお読みいただければ、ママに指示されることなくスムーズに動けて、信頼されるパパになれます。

私が2児のパパとして、実際に育休中に取り組んだことをお伝えしますので、
ぜひ最後までお付き合いください。
【PR】
育休パパがやること10選

「とるだけ育休」にならないために、育休パパがやるべきことは以下のとおりです。
- 赤ちゃんのお世話(お風呂とおむつ替え)
- 赤ちゃんの寝かしつけをマスター
- 家事の分担(料理・掃除・洗濯)
- 夫婦のコミュニケーションを大切にする
- 産後ママのケア(メンタルサポート・休息時間の確保)
- パパ自身のメンタルケアも
- 役所・保険の手続き(児童手当・医療費助成など)
- 育児に役立つ情報収集
- 育休中の家計管理&お金の準備
- 家族でお出かけして思い出づくり
この10選だけ抑えておけば、信頼されるパパになれること間違いなしです。
赤ちゃんのお世話(お風呂とおむつ替え)
赤ちゃんのお世話の中で、お風呂と着替えはパパでもできる大きな育児です。
授乳はママしかできないので、お風呂と着替えだけはパパが担えるようにしましょう。
◉お風呂
- まず、リビングなどでママに赤ちゃんの服を脱がしてもらって、パパはお風呂の中で赤ちゃんを受け取ると、楽に入れられます。
- 赤ちゃんを洗うときは、左手で後頭部をしっかり抑えながら、右手で洗っていきます。
- 爪は立てずに、指の腹で優しくマッサージするように洗ってあげてください。
- 洗った後、湯船に5分程度浸かったら、ママを呼んで赤ちゃんを渡して、すぐパパも出て赤ちゃんに保湿クリームを塗ってあげましょう。
◉着替え
最初のうちは、一日に何度もおむつ替えをする必要があるので、パパが替えられるとママの負担を減らせます。
うんちをしている場合は、おしりふきで拭いてあげます。
ポイントは、左手で両足首を使って持ち上げながら、右手でやさしく拭き取ることです。
うんちの量が多いと、股のスキマに入り込んでいることがあるので、足を優しく開いてあげてしっかり拭き取りましょう。
赤ちゃんの寝かしつけをマスター
赤ちゃんの寝かしつけは基本的に立って抱っこするため、足腰が強いパパが担うことをおすすめします。
また、寝る時に一緒にいることで、パパへの安心感が芽生え、寝かしつけ以外の時間もパパを好きになるきっかけになります。
寝かしつけるときのコツは、膝を軽く曲げながら抱っこすることです。
他のコツについても以下の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
寝かしつけをマスターして、子供とのリラックス時間を満喫しましょう。
家事の分担(料理・掃除・洗濯)
家事は「ママを手伝う」のではなく、「夫婦で分担する」意識を持っておきましょう。
出産はママしかできないかもしれませんが、家事はママが主体でなくてもいいからです。
例えば、
- 月・水・金はパパが料理する。
- 洗濯はパパが担当する。
など決めておくと、誰がやるか確認する手間が省けますし、自分の分担に責任感を持って取り組めます。
夫婦のコミュニケーションを大切にする

夫婦で育休をとっていると2人きりの時間が増えますが、こういう時こそ意識的にコミュニケーションを図ってください。
何気ない会話で構いません。
「○○くんの寝顔がかわいいよね。」
「この○○美味しいね。」
など、たわいもない会話でも、しないよりマシです。
注意点として、ママの話に意見したり、反論するのは控え目にして、「そうだね」と共感するようにしましょう。
自分の考えを伝えたい気持ちはわかりますが、ママは意見を求めていないことが多いです。
「どう思う?」と求められたときだけ、伝えましょう。
せっかく夫婦で長い時間を過ごせる育休ですから、コミュニケーションを大事にして仲良く過ごしましょう。
産後ママのケア(メンタルサポート・休息時間の確保)
出産後のホルモンバランスの変化により、産後うつとなってしまうママは多いです。
一番身近にいるパパが寄り添ってあげましょう。
「こうした方がいいよ」とアドバイスするよりも、「辛いよね」と受け入れる意識が大切です。
また、子供が小さいうちは授乳などで寝れないことも多く、メンタルが落ち込みやすい状態です。
ママによって眠くなる時間は異なると思いますが、眠たいときはしっかり寝かせてあげてくださいね。

私の体験では夕方にママが眠くなることが多かったですが、ママのコンディションを注視して判断しましょう。
パパ自身のメンタルケアも
ママのメンタルケアが大切な一方で、パパ自身のメンタルケアもおろそかにしてはいけません。
ママのサポートに徹するあまり、自分を追いつめてしまい、うつになってしまうパパもいます。
メンタルケアとしてのおすすめは、午前中にウォーキングなどの軽い運動をすることです。
日光を浴びながら運動すると、「幸せホルモン」と言われるセロトニンが分泌され、心の安定やストレス軽減につながるからです。
また、セロトニンは夜になると「睡眠ホルモン」と言われるメラトニンに変化し、体内時計を調整して自然な眠りを促します。
がんばりすぎず、自分の心身の健康を大切にしてくださいね。
役所・保険の手続き(児童手当・医療費助成など)
役所などの手続きもできればパパがやってしまいましょう。
役所へ直接行く場合があるので、動きやすいパパが行った方が楽だからです。
具体的には以下のような手続きがあります。
主体的に動いて手続きを完了させれば、ママに感謝されること間違いなしです。
育児に役立つ情報収集
育児・家事に追われるだけでなく、育児に関する情報をインプットするのも重要です。
自分の考えだけで育児をすると、偏りが出てしまうからです。
赤ちゃんのおしりの拭き方や、離乳食に関することなど、「自分がこれでいいんだ」と思ったことを疑いなく続けていませんか?
色んな情報をインプットした上で、日頃の育児で試してみることによって、自分に合った正しい手法が見つかりますよ。

パパにおすすめの育児本を以下の記事にまとめてますので、興味があるパパはぜひご覧ください。
育休中の家計管理&お金の準備

育休に入ると収入が減るため、家計のやりくりが重要になります。
育児休業給付金の支給額やボーナスの減額を理解した上で準備しましょう。
育児休業給付金=
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
出典元:厚生労働省HP
要するに、育休開始から6か月までは67%、6か月以降は50%に減ってしまうということです。
ただし、社会保険料や住民税の負担が減るため、実際の手取りは思ったほど減らないこともあります。
ボーナスについては、育休期間は査定対象外となることが多く、支給額が減るか、ゼロになる可能性があります。
事前に会社の制度を確認しておきましょう。
また、支出を抑えることも大切です。
支出を抑える際は、以下の3点を意識しましょう。
- アプリなどで全ての支出を見える化する
- 自炊を増やす
- 不要なサブスクを解約
事前に家計を見直し、無理のない範囲で節約しながら、安心して育休を過ごしましょう。
家族でお出かけして思い出づくり
育休中は家にこもることが多いので、家族でお出かけして気分転換するのも重要です。
赤ちゃんとのお出かけは大変ですが、公園や児童館、ベビーフレンドリーなカフェなど、無理のない範囲で楽しめるスポットを選びましょう。
短時間の外出でも気分がリフレッシュされます。
せっかくの育休期間ですから、家族で楽しい思い出をたくさん作りましょう!
【PR】
パートナーが喜ぶ「気が利くパパ」になる4つの方法

気が利くパパになるためには、以下の点を意識するのがおすすめです。
- 基本的にママを休ませる
- 「○○する?」ではなく「○○するね!」
- 育児スケジュールを把握しておく
- ママの話に対しては意見せずに共感する
この4つだけでも意識できれば、ママからの評価が上がりますよ。
基本的にママを休ませる
「ママはパパより大変だから休ませる」という意識を忘れないようにしましょう。
授乳が必要な時期は、数時間に一度は起きなければならないので、常に睡眠不足の状態です。
それに加えてホルモンバランスが悪いことが多く、体調が万全なことの方が少ないです。
もちろんパパ自身の体調も大切ですが、ママの方が疲れていると思いながら、家事を行うのががちょうどいいでしょう。
「○○する?」ではなく「○○するね!」
「この家事をした方がいいかな?」と思った時、やった方がいいか聞くのは避けましょう。
聞かれたママは「お願いしていいのかな?」とか「お願いしたら申し訳ないかな?」と考えることで精神的な負担になるからです。
宣言すれば、やらない方がよいときだけ指摘すればいいので、ママの負担を減らして気持ちも楽になり、スムーズに家事を分担できます。
育児スケジュールを把握しておく
必要な手続きのスケジュールを把握しておくと、ママに喜ばれます。
育児は毎日が忙しく、赤ちゃんのお世話に追われていると、つい予定を忘れてしまうこともあるからです。
予防接種や定期健診は、生後すぐから何度も受ける必要があり、種類や時期が複雑なので、忘れないように注意してください。
おすすめは、googleカレンダーなどのアプリでスケジュール共有できるようにしておくことです。
パパが「来週、健診があるね」と声をかけてくれるだけでも、ママは安心できますし、負担がぐっと軽くなります。
ママの話に対しては意見せずに共感する
ママから話をされたとき、意見するのではなく、共感の言葉を話すよう心がけましょう。
例えば、「今日はずっと泣いていて大変だった」とママが話したときに、「この時期はしょうがないよね」と否定しては悲しい気持ちになります。
「大変だったね」「それは疲れたよね」と共感の言葉をかけるだけで、ママの気持ちは軽くなります。
また意見を求められたときは否定せず、「そう思うのもわかるよ」「こういう方法もあるかもね」と 優しく提案することが大切です。
ママの気持ちに寄り添い、しっかり話を聞くことができれば、夫婦の信頼関係も深まりますよ。
【まとめ】パパのやるべきことをやって育休期間を充実させよう!
育休中のパパは「とるだけ育休」にならないよう、積極的に育児・家事に関わることが大切です。
赤ちゃんのお世話や家事の分担だけでなく、ママのメンタルケアや休息時間の確保も意識しましょう。
子供にとってパパ・ママはどちらも大切な存在で、育休中は長く一緒にいて愛を感じやすいので、たくさん触れてあげてくださいね。
今回紹介したことを実践していただき、ママから信頼される素敵なパパを目指しましょう!
【PR】
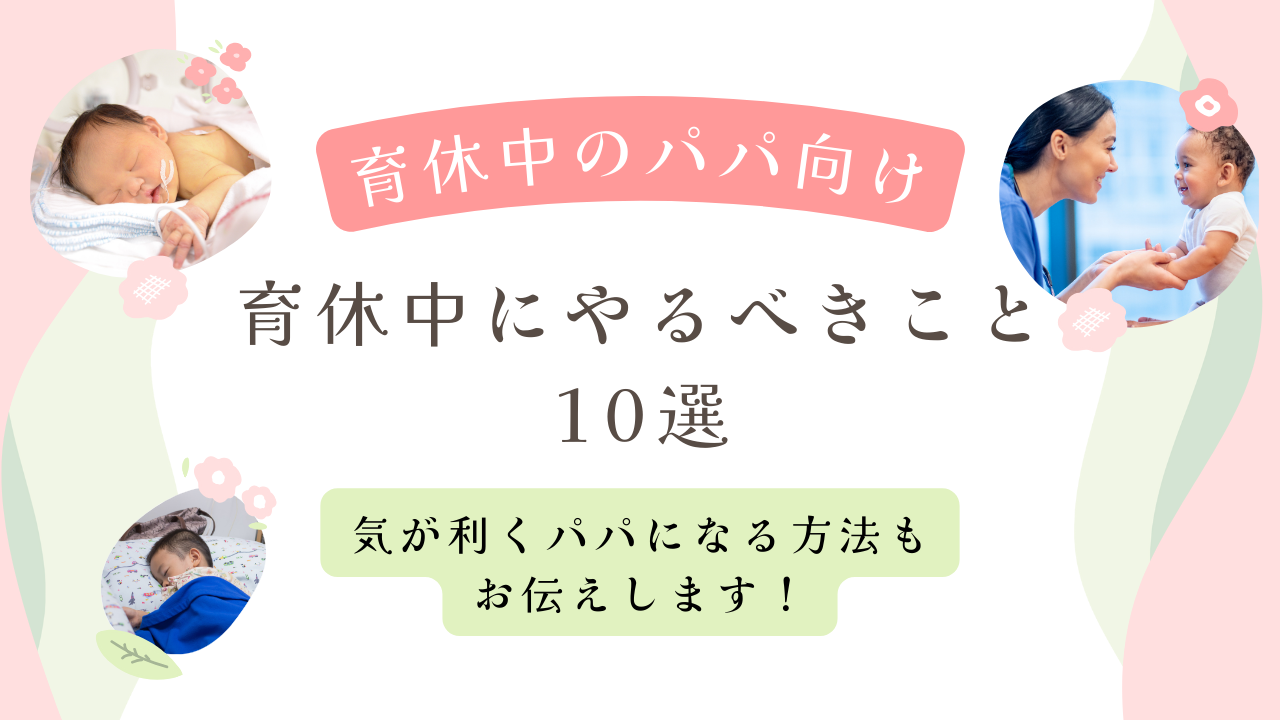

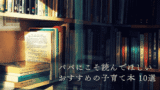


コメント