※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

子供を正しく叱るにはどうしたらいいの?
子供がパパの言うことを聞かなくて、ついつい叱りすぎてしまったな、と思うことがありますよね。
実は、怒るのと叱るのは別物で、NGな怒り方とおすすめの叱り方があります。
本記事では以下の点を解説します。
- 「怒り」と「叱り」の違い
- パパがやってはいけない怒り方8選
- 年齢別、怖がらせない叱り方のコツ

本記事をご覧いただければ、感情をぶつけずに「伝わる叱り方」がわかりますよ。
最小限の叱りに抑えて、子供と良い関係が築けるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。
【PR】
怒りと叱りの違い
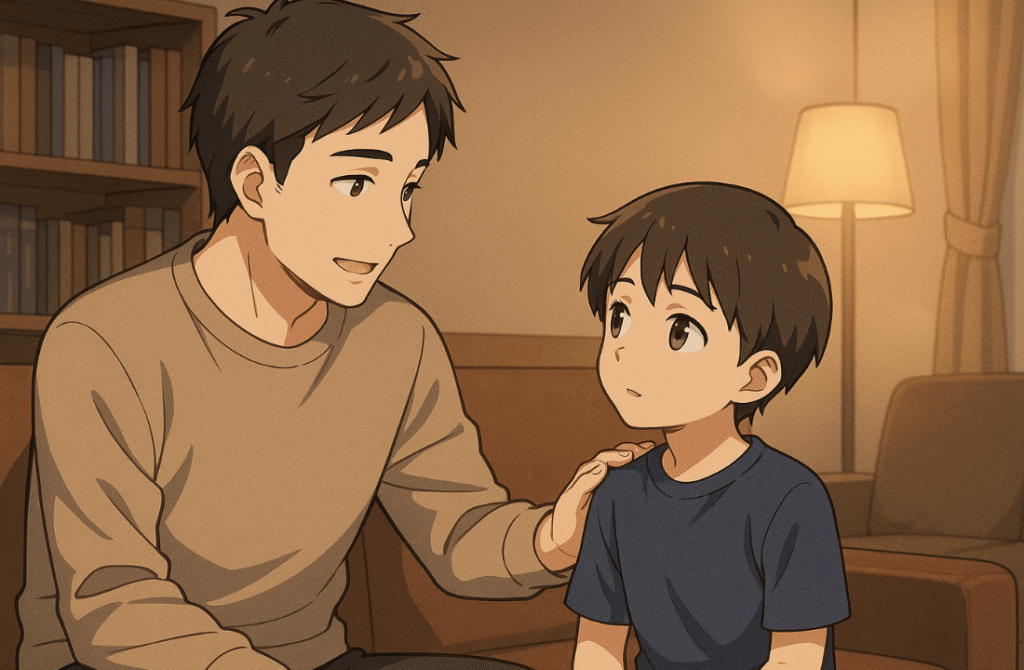
まず覚えていただきたいのが、
- 怒ると叱るは違うもの
- 怒るのはダメで、叱るのはOK
ということです。
怒りとは感情をぶつけること
怒りとは、自分の気持ちをコントロールできなくなったときに出る感情の爆発です。
子供に対して「なぜ言うことを聞かないんだ!」と怒鳴ってしまうのは、実は“心配”や“焦り”の裏返しです。
パパが頭ごなしに怒ると、「怖い」という記憶だけ残って、行動を直すよりも避けようとする反応が増えてしまうことも。

怒りの本質は、自分の理想と現実のギャップにあります。
「こうあってほしい」「ちゃんとしてほしい」という気持ちが強いほど、裏切られたように感じて、感情をぶつけてしまいます。
叱りとは子供に何かを伝えること
叱りとは、子供に「何がいけなかったのか」「次はどうすればいいか」を伝える教育的な行動です。
感情ではなく目的(しつけ・成長)に基づいて行うものです。
冷静なトーンで、子供の視点を尊重しながら伝えるのが理想です。
【NG例】パパがやってはいけない怒り方8選
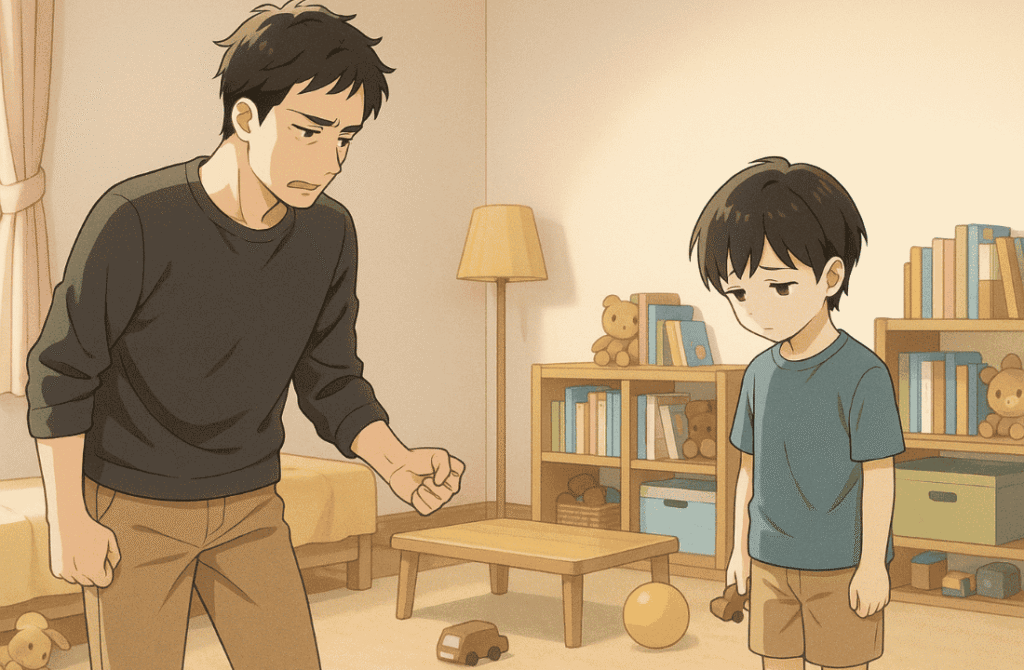
具体的に、パパがやってはいけない怒り方を8つ紹介します。
1.感情的に怒鳴る
子供が危ないことをしたり、言うことを聞かなかったりすると、つい声を張り上げてしまいますよね。
でも、怒鳴られた子供は“怒られた内容”ではなく、“パパの怖い顔”しか覚えていません。
怒鳴ると、子供の脳は「防御モード」に入ってしまい、言葉が届かなくなります。
大切なのは、叱る前に一度深呼吸することです。
6秒ルールといって、怒りの感情は6秒我慢すればピークを過ぎるといわれています。
その6秒を意識して深呼吸するだけで、言葉のトーンも穏やかに変わります。

怒らない子育てについては、以下の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。
2.長時間叱り続ける
叱る時間が長くなるのはNGです。
子供は「何が悪かったのか」がわからなくなるためです。
最初は真剣に聞いていても、途中から「早く終わらないかな…」と心を閉ざします。
叱るときは、ポイントをひとつに絞って短く伝えるのがコツです。
たとえば、
と、行動と理由を簡潔に伝えましょう。
目安として、叱る時間は1分以内にしましょう。
叱る長さよりも、「次にどうすればいいか」を意識するのが大切です。
3.過去の失敗を持ち出す
「前にも言ったよね」、「また同じことをして」とつい口にしてしまうことがあります。
けれど、過去を蒸し返されるたびに、子供は自分を責める気持ちを強くしてしまいます。

叱るのは、今起きたことだけにしましょう。
今回のことをどう直せるか、一緒に考える姿勢を見せてあげると、子供も前向きになります。
4.人格を否定する言葉を使う
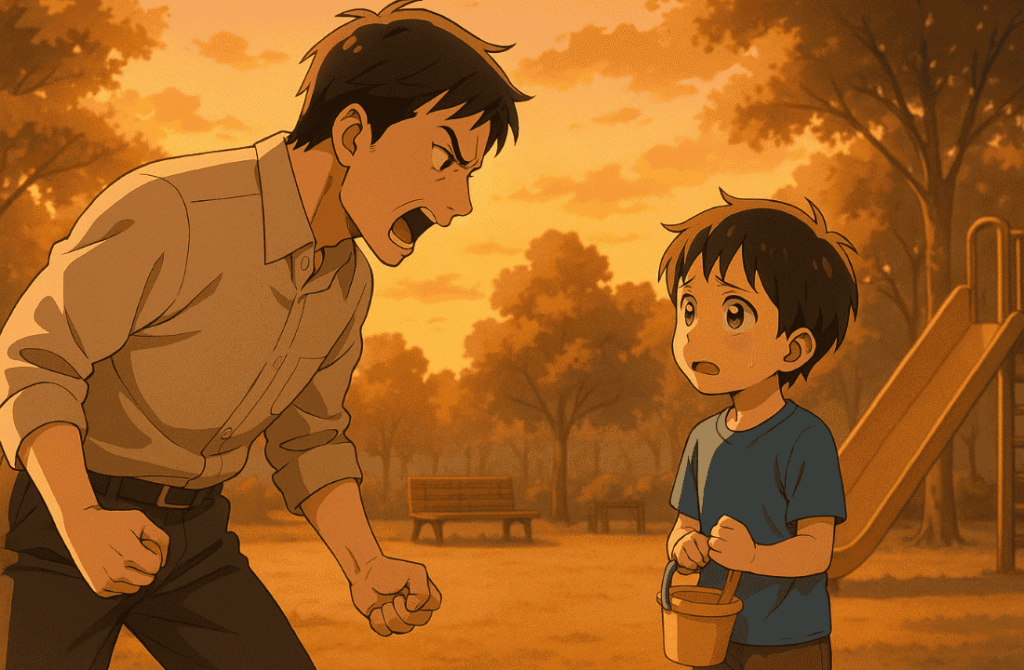
「できない子」や「どうしようもない子だね」などの、その子の人格を否定する言葉は心に深く残ります。
叱るときは、あくまで行動だけを指摘します。
片づけをしなかったことを注意しても、子供そのものを責めないように気をつけましょう。
行動を正しながらも、あなたのことは大切だという気持ちを伝えるのが、本当の意味での叱る姿勢です。
5.誰かと比較して叱る
兄弟や友だちと比べてしまうのも、避けたい叱り方です。
他の子と比べられると、やる気よりも劣等感のほうが強くなります。
昨日より少しできたね、前より頑張ったねというように、比べるのは過去の自分とだけ。
小さな変化を感じることで、子供は自信を積み重ねていきます。
6.決めつけて叱る
「どうせやらない」、「また同じでしょ」と言い切ってしまうと、子供は自分を信じられなくなります。
叱るときこそ、できると信じてあげることが大切です。
信じてもらえることで、子供はもう一度挑戦する力を取り戻します。

パパの信頼は、子供の強さを育てる大きな支えとなりますよ。
7.パパやママもできていないことについて叱る
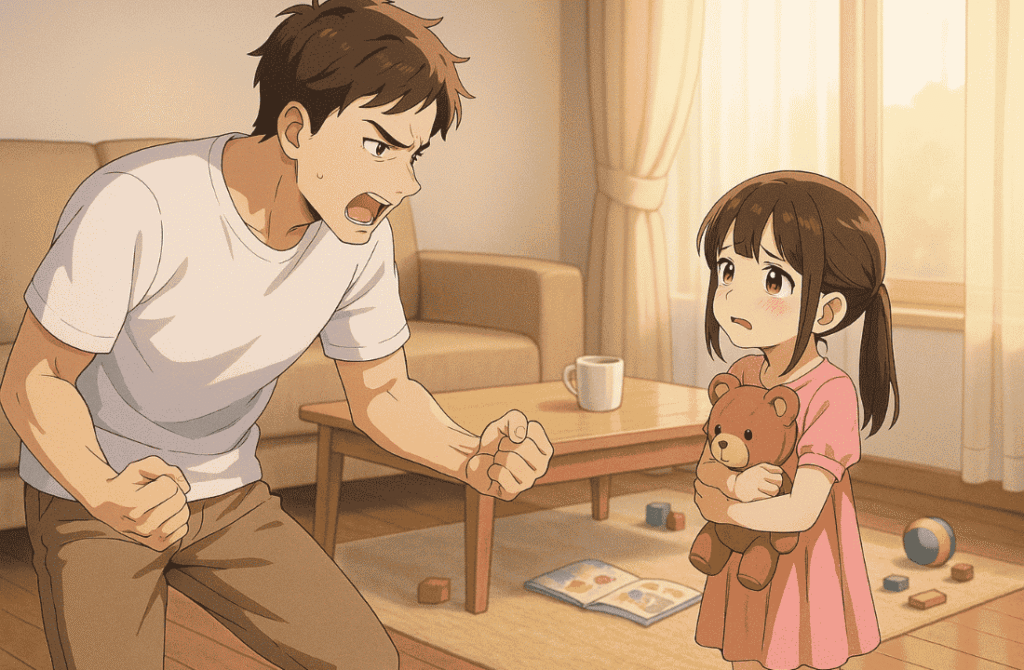
・自分の荷物が片づいていないのに、子供にだけ片づけを求めていませんか?
・自分はスマホばかりいじっているのに、子供の動画視聴を注意しすぎていませんか?
子供はまず、親を手本にして生きていきます。
親ができていないことを叱っても、説得力は生まれません。
まずは自分が見本を見せるのが、何よりの教育になりますよ。
8.パパとママの期待を押し付ける
「頑張ってほしい」「失敗してほしくない」という思いが強すぎると、いつの間にか子どもに期待を押し付けてしまうことがあります。
自分は失敗したから、子供には失敗させたくないという気持ちは痛いほどわかります。

でも、子供の人生は、パパの人生の2週目ではありません。
子供の人生は子供のものなので、パパはあくまでもサポートすることに徹しましょう。
【PR】
【年齢別】パパを怖がらせない正しい叱り方のコツ
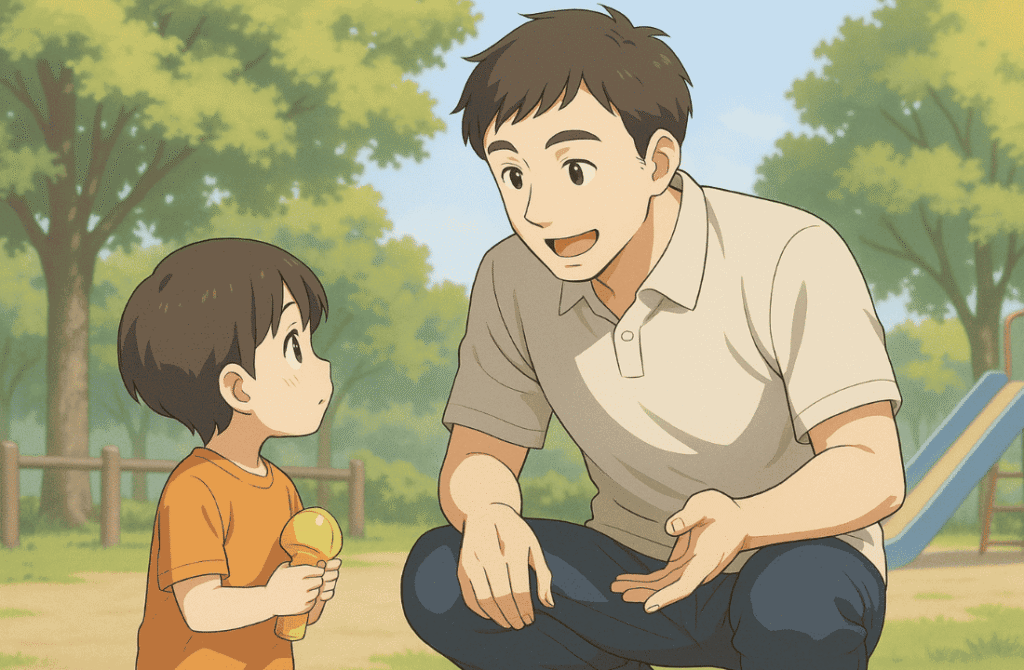
具体的にどのように叱ったらいいのかを、年齢別に解説します。
2〜3歳|短く、行動を注意する
この時期は、まだ言葉の理解が発達途中で、長く説明しても伝わらないことが多いので、短く、シンプルに伝えるのがポイントです。
ただし、「だめ」だけで終わらせず、すぐに正しい行動を示してあげましょう。
たとえば、
道路に飛び出しそうになったときは、「危ないからパパと手をつなごうね」と簡潔に伝えてください。
怒られた怖さを残さず、「パパは君を守りたいから言っている」と伝えることで、信頼が深まります。
4〜6歳|ダメな理由と具体例を説明する
4~6歳は少しずつ考える力が育ってくる時期です。
理由(なぜいけないのか?)と、具体例を説明すれば、子供なりに納得できるようになります。
たとえば、おもちゃを投げたときは、以下のとおり。
「壊れちゃうから投げないほうがいいよ。」(理由)
「壊れちゃって遊べないのは嫌でしょ?」(具体例)
また、片づけをしないときは、以下のように言ってみましょう。
「片付けておけば、明日遊ぶときに見つけやすいよ」(理由)
「トランプで遊ぼうと思ったときに、どこにあるかわかってると、すぐに遊べるよね」(具体例)

ただ、叱るよりも、
理由(なぜそうしたほうがいいのか)と、
具体例(例えば、こういうときにいいよ。)
の2点を伝えてくださいね。
小学生|自分で考えさせるような質問をする
小学生になると、叱るよりも「どう思う?」と問いかける方が、子供が自主的に行動できます。
パパは、あくまでも、きっかけだけを与えるようにしましょう。
たとえば、宿題を忘れたときに、どうしてできなかったのかを尋ねてみましょう。
「時間が足りなかった」
「やる気が出なかった」
など自分の中で整理できれば、それだけで次につながります。
”老子”の有名な言葉で、「魚を与えるのはなく、魚の釣り方を教えよ。」というものがあります。
大人になったら、自分で魚を釣れるようにならなければいけません。
小学生の頃から、ただ正解を与えるだけでなく、考えることについても教えてあげましょう。
【まとめ】パパは怒るのではなく”伝わる叱り方”をしよう!
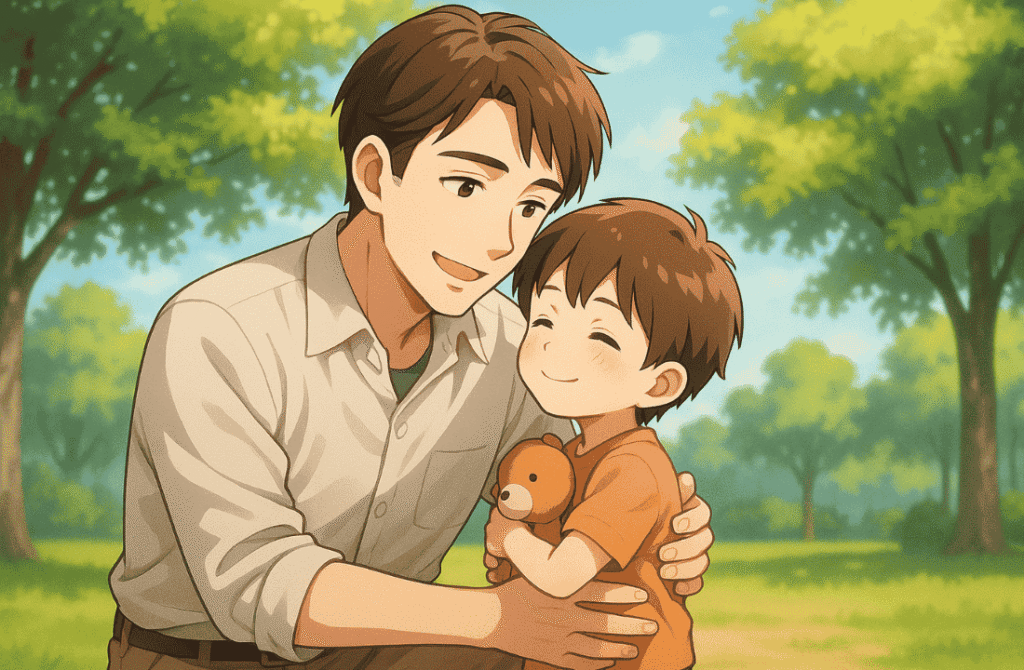
叱ることは、子供を傷つけるためではなく、成長を支えるための大切な時間です。
感情をぶつけるのではなく、冷静に伝えることで、子供の心に届きます。
叱るたびに少しずつ、親子の絆は深まっていきます。
今日からは、「怒る」ではなく「伝える」叱り方を意識していきましょう。

私も感情的になることは多いので、皆さんと一緒に実践していけたら嬉しいです。
【PR】
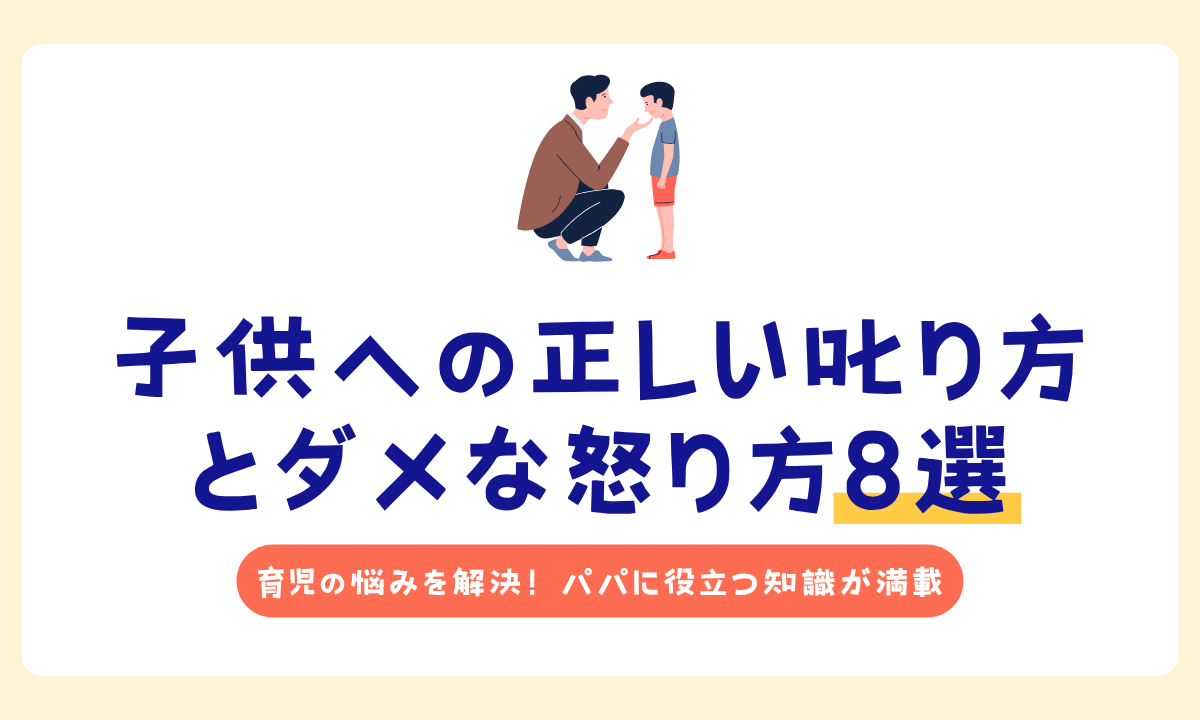



コメント