※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

パパ育休って本当に必要?
実際に育休制度を利用しても「とるだけ育休」と言われたり、周囲から理解されないケースがあります。
しかし、正しく向き合えばパパにもママにも赤ちゃんにもメリットがあります。
本記事では、パパ育休のメリットとデメリット、もし取らなかった場合の代替策をわかりやすく解説します。

私も育休を取りまくっておりましたが、全く後悔せずに過ごせています。
皆さんの育休取得を考えるヒントをお伝えしますので、迷っているパパはぜひ最後までご覧ください。
【PR】
出来立てが届く【つくりおき.jp】パパが育休を取る3つのメリット|「とるだけ育休」にならないために

パパが育休を取るメリットは以下の3点です。
1.ママの心身の負担を減らせる
出産後のママは、体の回復が不十分なまま昼夜を問わず赤ちゃんのお世話に追われます。
授乳や夜泣きによる睡眠不足に加えて、家事もこなそうとすることで心身ともに限界を感じやすい時期です。
パパが育休を取って一緒に育児や家事を担えば、ママは安心して体を休められます。

たとえば、おむつ替えやお風呂、買い物などをパパが担当するだけでも負担は軽減されますよ。
2.赤ちゃんとの信頼関係を築ける
赤ちゃんは抱っこや声かけ、スキンシップを通じて「この人は安心できる存在だ」と感じていきます。
特に生まれて間もない時期にパパが積極的に関わることで、ママだけでなくパパにも強い愛着を抱くようになります。
また、国立成育医療研究センターの研究でも以下のように、父親が育児へ関わるメリットの可能性が示されています。
乳児期における父親の積極的な育児への関わりが子どもが16歳時点での心理的ウェルビーイングの低下のリスクを減らす可能性が示唆された。
引用元:国立成育医療研究センター
赤ちゃんの成長に合わせて表情が豊かになったり笑顔を見せてくれたりするのを間近で体験できるのも大きなメリットです。

スキンシップの工夫としては、絵本の読み聞かせもおすすめですよ。
3.自分自身の成長の機会になる
泣き止まない赤ちゃんに試行錯誤したり、家事と育児を両立させようと工夫したりする中で、自然と忍耐力や柔軟性が養われます。
また、相手の気持ちを想像して行動する力が育つので、夫婦関係だけでなく仕事の人間関係にも良い影響を与えます。

私も育休中、家事や育児をする中で、「マルチタスクに強くなった」と感じるようになりました。
育休は単なる休みではなく、パパが一回り大きく成長するチャンスと捉えると、前向きに取り組めるはずですよ。
パパ育休のデメリット|いらないと言われる理由
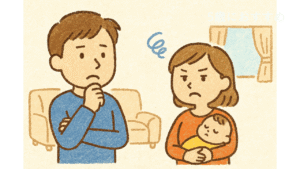
パパ育休には以下のデメリットがあり、しばしば「いらない」と言われてしまいます。
収入が減る可能性がある
育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されますが、手取りが100%になるわけではありません。
参考:厚生労働省HP
特に住宅ローンや教育費など固定費が多い家庭では、収入減が大きな不安要素になります。
さらに、ボーナス査定や会社の給与体系によっては影響が出る場合も多いでしょう。
家計のシミュレーションを事前に行い、どのくらいの期間なら安心して育休を取れるのかを夫婦で話し合っておくのがおすすめです。
ママから「役に立たない」と思われることもある
育休を取ったのに「全然動かない」「ゲームばかりしている」となると、ママにとってはむしろ負担が増えます。
SNSなどでは「とるだけ育休」という言葉も見られ、指示待ちのパパにイライラするママの声も多いです。
せっかく育休を取得するなら、自発的に行動して「役に立つ」と感じてもらえるようにしましょう。
職場でのキャリアに不安が残る
男性が長期間育休を取ることはまだ一般的ではなく、復帰後にキャリアに影響があるのではと不安を感じる人もいます。
上司や同僚の理解が得られず「出世に響くかもしれない」と考えるのも無理はありません。

私も、同僚から「なんでパパも育休取るの…?」と不思議がられました。
ただし、最近は企業側も積極的に男性育休を推進しており、制度を活用した経験が評価されるケースも出てきています。
生活リズムが乱れやすい
赤ちゃんのお世話は昼夜を問わず続夜中の授乳や寝かしつけを手伝うと、どうしても睡眠不足になります。
特に今まで規則正しい生活を送ってきたパパにとっては大きなストレスになるでしょう。
また、生活リズムが乱れると、体調不良やイライラの原因になり、夫婦関係に悪影響が出ます。
だからこそ、無理をせず夫婦でシフトを組んだり、役割分担したりと、工夫が必要です。
パパ育休を取らない場合の対処法5選

パパ育休を取れない場合でも、以下の5点を実践すれば育児に関わることができますよ。
1.仕事後や休日にできることを明確にする
育休を取らなくても、育児に参加できる方法はたくさんあります。
例えば、「夜は必ず寝かしつけを担当する」「休日は丸一日子供と過ごす」といったことをママに宣言してみてはいかがでしょうか。
曖昧なままだと「結局ママが全部やっている」という状況になりやすいため、できることを明確にしておきましょう。
2.時短勤務や在宅勤務を活用する
育休を取らなくても、柔軟な働き方を工夫すれば家庭に関われます。
時短勤務や在宅勤務ができる環境であれば、送り迎えやお風呂、寝かしつけなど育児の一部を担うことが可能です。

近年、多くの企業で男性の柔軟な働き方を後押しする制度が整ってきているのも、私たちにとって追い風になります。
うまく活用すれば、育休を取らなくても育児参加の機会を増やせるので、まずは自分の職場の制度を確認するのがおすすめです。
3.ママの「一人時間」を意識的に確保する
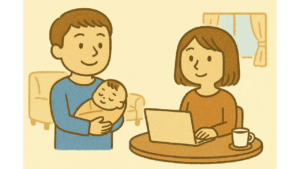
産後のママは昼夜を問わず赤ちゃんと一緒に過ごしているため、心が休まる瞬間がほとんどありません。
だからこそ、パパが意識して「ママが一人になれる時間」を作ってあげることが大切です。
短い時間でも子供を連れて散歩に出たり、休日にパパが積極的に遊び相手になったりするだけで、ママはリフレッシュできます。
4.家事・育児のアウトソースを検討する
宅配弁当や家事代行サービス、ベビーシッターなど、外部の力を借りるのも効果的です。
「パパが育休を取れないからこそプロの手を借りる」という発想に切り替えると、家庭全体が楽になります。
費用はかかりますが、ママやパパの体力・精神力を守る投資と考えると価値があります。
子供が健やかに育つのを最終目標にして、使える力は使っていきましょう。
【PR】
5.夫婦のコミュニケーションを増やす
どんなに忙しくても、夫婦の会話を大切にするのが最も重要です。
お互いの気持ちや状況を言葉にするだけで「一人で抱え込んでいる」という孤独感を防げます。
特にパパは「どうしたら助かる?」と聞く姿勢を持つと、ママは安心して気持ちを打ち明けられるようになります。

ただし、いつも「何をしたらいい?」と聞きまくってると、嫌がられるのでほどほどにしましょうね。笑
時には、聞かずにやってしまってから報告する姿勢も大切です。
【まとめ】パパ育休は「取る・取らない」よりも「どう関わるか」が大切!
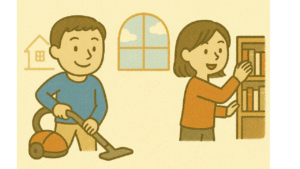
パパ育休には確かにメリットもデメリットも存在します。
重要なのは「取るかどうか」だけにこだわるのではなく、家族にとってどのように関わるのがベストかを考えることです。
主体的に動くパパであれば、育休を取っても取らなくてもママにとって心強い存在になります。
本記事でご説明した内容を参考にしていただき、夫婦でしっかり話し合い、家族に合った形を選んでいただければ嬉しいです。
【PR】
出来立てが届く【つくりおき.jp】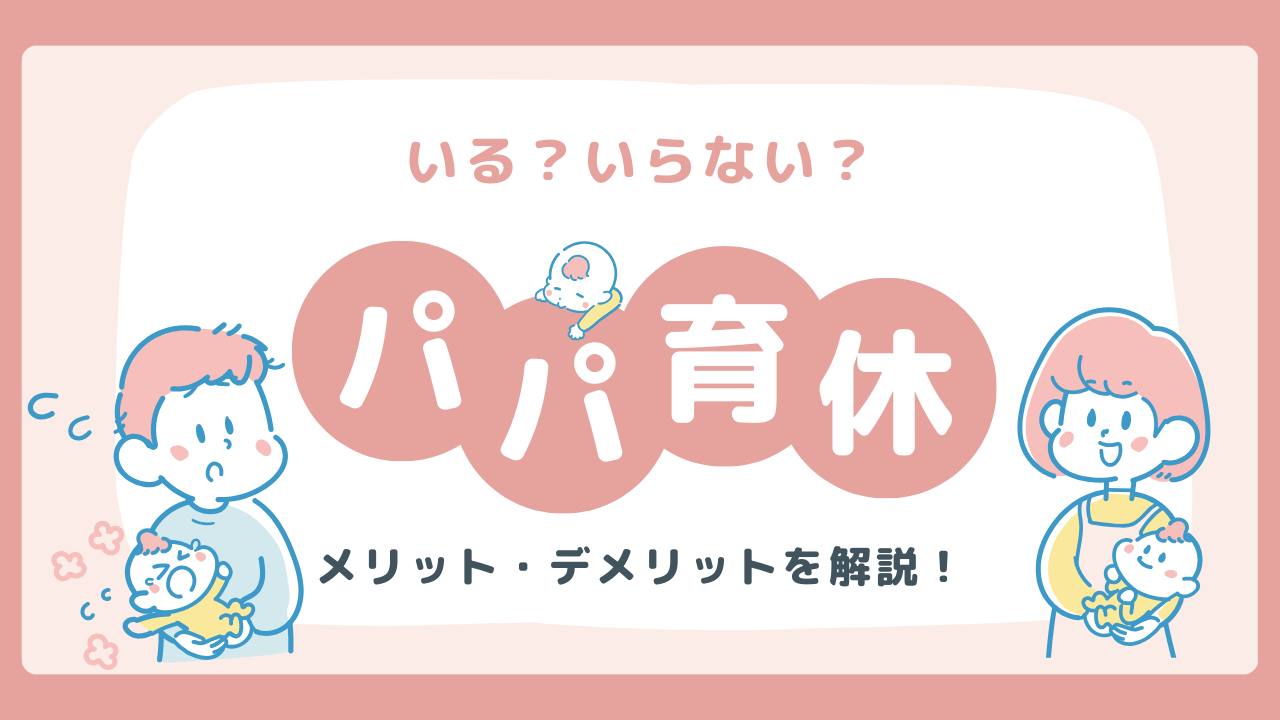

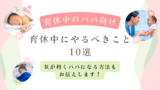

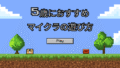
コメント